
|
間がかかるということである。5分かかってやっと60%元に戻るという具合である。
3. 望遠鏡
航海中にいろいろなものを見たり、方位を測ったり、計器類を監視するためには人間の唄とそれに対する判断が重要になる。状況判断は経験がものをいうとしても、眼は個人に備わったものであるから、何をおいても常に最良のコンディションに保っておく必要がある。
しかし、人間の眼にも見える限度があり、それを補うのが双眼鏡(望遠鏡)である。
明治38年(1905年)5月27日、ロシア・バルチック艦隊と日本連合艦隊との大海戦(日本海海戦)は日本艦隊の大勝利のうちにその決着がついた。旗艦スワローのロシア艦隊司令長官ロジェストウェンスキー中将は重傷を負い、駆逐艦ベドウィに移乗してウラジオスットク軍港に向けて逃走中、翌28日の午後、捜索中の日本駆逐艦漣(さざなみ)に発見され追撃を受けて捕らえられた。
駆逐艦漣はベドウィの吐く黒煙(当時は石炭が燃料であった)を発見したのだ。そして,この黒煙を捉えたのは漣乗組の塚本中尉の双眼鏡であった。この双眼鏡は、連合艦隊司令長官東郷平八郎大将の所持していたものと同種の、ドイツの力ール・ツァイス社のプリズム双眼鏡(10倍)で、当時日本海軍では東郷と塚本の二人しか持っていなかったといわれる。塚本中尉は、かって旗艦三笠で東郷司令長官の携帯する双眼鏡がドイツ製の世界最新鋭のものであることを知り、それにひきかえ漣では旧式の遠目鏡(とおめがね)しかないことを憂い、大まい350円という当時としては超高価なもの(警視庁巡査の給料が10〜15円程度)であったが借金に借金を重ねて急ぎ購入し、これを携えて日本海海戦に臨んだのである。そして、その双眼鏡のおかげで敵艦隊の司令長官を捕らえるという大殊勲をたてたのであった。
3.1 望遠鏡と入射瞳および射出瞳
前方から眼の瞳孔を見ると、その前にある角膜と前房水が拡大鏡の作用をするため、瞳孔径は実際のものよりも1.13倍の大きさに見える。その時の拡大された瞳孔の像を入射瞳といい、角膜頂点からおよそ3.05mmのところにつくられる。通常いわれる瞳孔径とは入射瞳の直径で、瞳孔の見かけの大きさである。
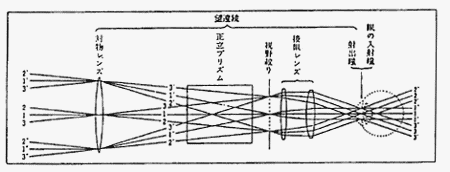
図3.1 望遠鏡のレンズ構成
前ページ 目次へ 次ページ
|

|